ISN島内キャンパスの保護者様 吉澤茉帆さんインタビュー:「一人ひとりが尊重される社会に」
吉澤さんが考えるウェルビーイングと女性の権利、そしてこれからの地域社会のかたち。

地域のウェルビーイングと世界水準という視点から
栗林:
地域のウェルビーイングと世界一水準というテーマで、吉澤さんが今、何を取り組まれているか教えていただけますか?
吉澤さん:
私が一番目指したい世界水準の分野で言うと、女性の権利や健康のようなところが遅れてるなというところから始まっています。
選択的夫婦別姓という制度がきっかけではあったんですが、それを取り組んでいくうちに、結婚や出産、妊娠など、そういったことに関わる女性の健康や安全が、子どもの死亡率は低いけど健康か安全かと言われると、そうでもないような現実があるなということに気がつきました。
そこを少しでも改善したいと思ったのがきっかけです。
「気づいたきっかけ」はどこにあったのか
栗林:
気がついたというのは、どのような時でしたか?
吉澤さん:
何だろうな…その夫婦別姓の話で言えば、結婚するときに、それぞれが/どちらかが苗字を変えるという選択しか今なくて、「どちらも変えない」という選択肢がないんですよ。
単純に、なんか忘れられてるというか…と思ったら、そこにすごく意味を持たせている人たちがいるっていうのを知ったんですよね。
今は、結婚している人たちの95%は女性の苗字を変えている現状で、女性に改姓の負担を負わせることで、その“家のものになる”ような形だけが残っている。
制度としては別に家の戸籍に入るとかはないけれど、その形式が残っているというのを学んでいった時に、「苗字なんて」と思う人もいるけれど、ちょっとした選択をさせないことが女性を不便にさせたり不利益を負わせたりしてるんだな、というふうに気がつきました。
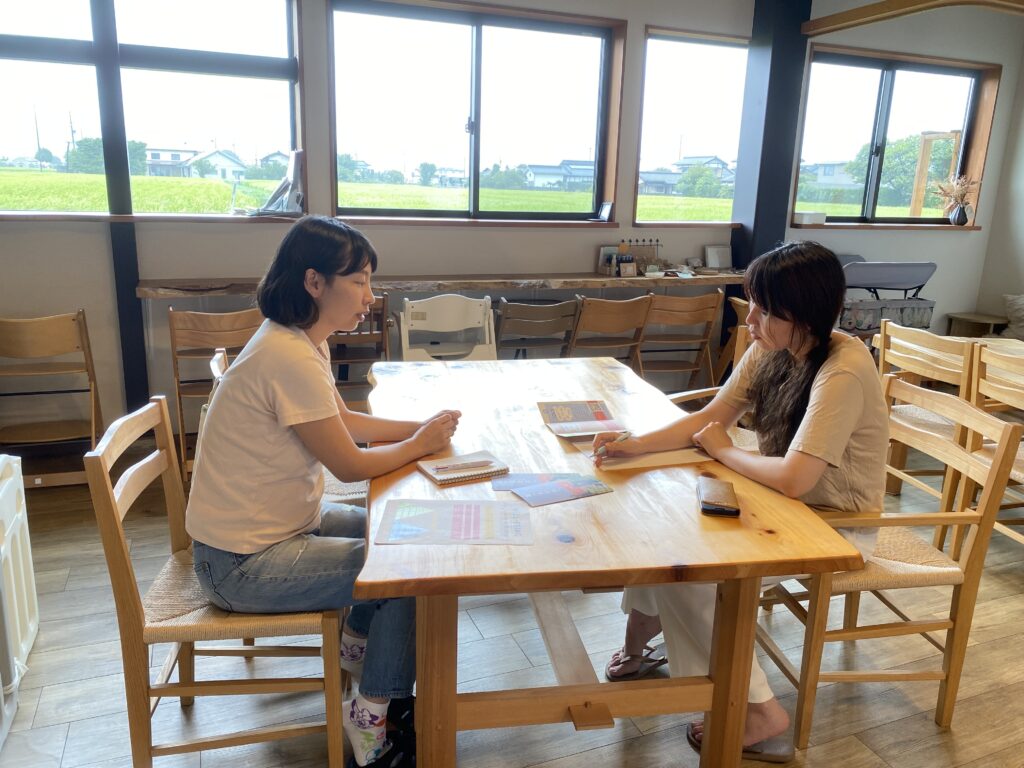

「選択肢がない」ことの違和感と気づき
栗林:
選択というのは前からあったかもしれないけど、その選択があると本人たちが気づいていなかったり、大多数の人がそうだからと言って苗字をどっちの名にするかを決める。
そういう風習だったり文化になってしまっていて、そこのいいところももちろんあるだろうけど、それでネガティブなところも気になったとか。
吉澤さん:
そうですね。ネガティブなことがすごく気になりますね。
世界の中でそういうことができないのは日本だけって言われてるんですよ。
この国は、どちらかが苗字を変えるとかじゃなくて、どちらも変えないという選択ができるとか、ルーツを大事にするから変えないのがスタンダードだったり、結婚と名字を変えるということを切り離そうというところもあるのに、日本はそこをくっつけて女性を家に入れようとする、みたいなことにつながる制度があるんですよね。
「市議に出る」という決意の背景にある気づき
栗林:
そこを疑問に思わない辺りが、多分疑問だったんじゃないかなって。
どっちかを選べばいいけど、それが自然になってて。
一番最初に言ってた女性の権利だったりとかっていうのが、おろそかになってるんじゃないかみたいな。
そんなきっかけがあって、今回、市議を目指そうという動きになっている。これって大きなステップアップだと思うんです。
どんな変化があって、それをやってみようかな、市議に出てみようかなと。
吉澤さん:
制度上、女性の権利があんまり大事にされていないところが残っていると気づいた。
それを議論して決めていく場所に女性が少ないっていうことにも気づいて。
そこにはやっぱり、女性だからいいってわけではないけど、一定数の多様性というかバリエーションがないと、その困りごとをキャッチできる人が少ないなって。
誰かがなってくれたらいいな。でも、待ってるだけじゃなくて、自分の関心があって家族の協力とか理解があるんだったら、自分がまずチャレンジしないと、「誰かやってよやってよ」じゃ増えないなと思って。やってみようかなっていうステップになっています。
「声が届く社会」を目指して
栗林:
今ここに挙げている世界観として、例えば「こうあるべき」より「自分らしい選択ができる社会」とか、「どんな家庭の形でも楽しく子育てができる街へ」、そして「声を届けたいと思った時に届くような仕組みを」。
これって、吉澤さんの個人的な体験からですか? それとも客観的に社会を見て、これは変えた方がいいんじゃないかと思った部分ですか?
吉澤さん:
自分も子供を産む前は「お母さんってこうしないといけないのかな」みたいなイメージにすごく縛られてたなって。
でも実際子供を産んで育ててみたら、すごく子育てに対する価値観ってバラバラ、それぞれだなって思って。でも、それでいいじゃんって思ったんですよ。
自分はこれが大事、ここが重要だって思うことを子供に伝えたり、一緒にやっていけばいい。
でもそれが周りから、「それはおかしい。お母さんなんだから料理作らないと」とか言われるのは、苦しいじゃないですか。
当事者じゃない人の押し付けみたいなことから、できるだけ自由で、自分が選択した方がいいなっていうのは、自分の体験から思ったことですね。
「安心感のある社会」を子どもたちに
栗林:
じゃあ、それを実現するには話す場とか、対話が大事になってくる?
吉澤さん:
そうですね。話をするっていうのはすごく大事。
それぞれ価値観が違うからこそ、ためらうこともあると思うんですけど、話すことで「自分が何を望んでるのか」「何を大事にしてるのか」に気づけると思ってて。
そういう話をする場所を作れるといいなと思っています。
栗林:
そこに集まる人たちって、どんな人たちをイメージしていますか?
吉澤さん:
うーん…迷ってる人とか、「これでいいのかな?」って不安がある人が来るイメージをしてるかもしれないです。
強い主張がある人より、自分はこうかなって思ってるけど、どうなんだろう?みたいな人。
そういう人が集まって、お互いの考えを聞くことで「自分の選択でいいんだな」って思えるような、そんな場になったらいいなって。

最後に:目指す社会とこれから
栗林:
最終的に、その場やコミュニティが育っていった時、どんな社会になってると思いますか?
吉澤さん:
なんかそれこそ「安心感がある社会」っていうのがイメージですね。
考え方が違っていても、バックグラウンドが違っていても、お互いがその地域やコミュニティにいていいんだって思える安心感。
そういう地域を、子どもたちに渡したいなってすごく思います。
栗林:
なるほど。これからの活動も、興味深く見守らせていただきます。
お話をする人も嬉しいし、いろんな話を聞きたいっていう人たちと一緒に活動していけたらいいですね。
吉澤さん・栗林:
ありがとうございました。

